Profile 稲葉 上道(いなば たかみち)
1972年、東京都生まれ。大学院研究室在籍時にハンセン病資料館が学芸員を募集していることを知り、2002年に同資料館初の学芸員として採用される。その後、学芸課長などを歴任。2016年初頭からパワハラ被害を受けるようになり、2018年、新設された職員1人のみの資料管理課に配属される(事実上の追放人事)。職場における恫喝、排除などが起きてきたことを受け、2019年9月に労働組合「国家公務員一般労働組合国立ハンセン病資料館分会」を立ち上げる。2020年3月、受託者が変わるタイミングで不採用となり、18年間勤務したハンセン病資料館を去ることとなった。現在は復職を求め、団体交渉、裁判などを通じて闘争中。
「学び直し」の過程で
出会ったハンセン病資料館
──稲葉さんは、なぜ博物館の学芸員になろうと思ったんですか。
最初に学芸員になりたいと思ったのは大学を卒業するときで、1995年のことだったと思います。学芸員課程を履修していて、資格は取れる見込みだったので、どうせならその資格を活かして仕事ができたらいいなと考えたんですね。
じつはハンセン病資料館に勤める前に、地方の美術館みたいなところに就職していたことがあるんです。縁もゆかりもない地方都市でしたが、学芸員資格を活かせそうだ、ということで応募しました。
──それは初耳です。
結局1年ほど働いたんですが、そこでの仕事内容というのが、ちょっと詐欺的な感じといいますか、これはどうなのかなと思う部分が多かったんですね。たしかに絵は飾ってあるんですが、目的はお客さんにお土産品を売ることで、「幼稚園や小学校で割引券配って、お客さん呼んできて」と言われたりとか。でも正直、子どもたちを呼んできて見せるほどの展示ではなかったですし、そういうことをしたくて学芸員になったわけじゃないなあ、と思いまして、辞めることにしました。
そういう現実を知ったことで、美術館、博物館とは何なのか、学芸員とはどんな仕事をすべきなのか、もう一度勉強し直すべきだと感じました。それで東京に戻ってきて、あらためて大学院へ行こうと思ったんです。もう一度大学に行き直せばよかったんですが、大学を卒業した後だったので、次は大学院しかないんだろうと勝手に思い込んでいたんですね。
──ハンセン病資料館を知ったのは、大学院時代のことですか。
大学院では研究室の手伝いもしていたんですが、そのときにハンセン病資料館へ見学に行く機会があったんです。それまではハンセン病のことなど、まったく知らない状態で、知っていたことといえば1996年の「らい予防法」が廃止になったことくらい。実際に資料館展示を見て、「こんなことになっていたのか」と思いました。
資料館に来るまでハンセン病回復者の方がすぐとなりにある療養所(*国立療養所多磨全生園)に住んでいることも知らなかったですし、「国はこんなことをしてきた」「当事者は過去にこういう目に遭ってきた」などの歴史的事実についても、まったく知らないことばかりでした。率直に言って、かなり驚きました。

──そんな稲葉さんがハンセン病資料館に勤めようと思ったのは、なぜだったのでしょう。
大学院で修士二年が終わるときに就職先も決まっていない、修士論文も書けていない、これは三年目に突入するのは確実、という状況になりまして、これはどうしたものかと思っていたんですが、そのときたまたまハンセン病資料館で学芸員を募集しています、という話が研究室にきたんですね。指導教官から「資料館の学芸員になってみてはどうか」と言われたのが、直接のきっかけです。
採用も公募などといった段取りはまったくなくて、「学芸員資格持っていて働きたい人がいたら、とにかく連れてきて」みたいな感じだったようです。面接は一応ありまして、当時資料館の運営委員長をしていた成田先生(*現ハンセン病資料館・館長)、実際に資料館を切り盛りしていた佐川修さん(多磨全生園入所者自治会副会長)、それから当時の雇用主である藤楓協会から大谷藤郎理事長、この3人の方から話を聞かれました。
研究室に最初に話がきたのが2001年の年末か、2002年の年明けくらい、面接を受けたのが2002年の春先だったと思います。ハンセン病資料館の学芸員になったのが2002年の5月1日ですから、本当にあっという間でした。
手探り状態から始まった
ハンセン病資料館学芸員の仕事
──2002年当時のハンセン病資料館は、どんな感じでしたか。
今とは雰囲気も全然違いました。開館時間も午後からで、午前中は開いてなかったです。場所は今と同じですが、奥の増築棟(*視聴覚ホールや展示室などがある部分)はまだなくて、建物も手前側だけ。こじんまりとしていて、いかにも手作りという感じでした。
「学芸員として、この仕事をしてください」という具体的指示は、当初まったくなかったんですね。そこで、この資料館には何が足りていないのか、自分なりに観察をして、やるべきと思われる仕事を自分で設定して、それを毎日地道にやっていきました。語り部活動などは、当時からかなり目だっていて、内容も充実していましたし、すでに資料館の中心的活動にもなっていましたので、これは自分が手を出す領域ではないだろうと。
ところがそれ以外の部分を見ていくと、博物館として、ここはもうちょっと足した方がいいなと思う部分が、わりとあちこちにありました。たとえば資料の整理であったり、収蔵品のリスト作成といった部分です。じつは後になって実物資料についてはリストがあったことが判明したんですが、当時、大量に未分類のまま保管されていたのは文書資料でした。まずはこれを整理してリスト取りしていく必要があるだろうということで、そこから作業を始めました。
もうひとつは全国15ヵ所(*国立13園、私立2園)の療養所から送られてきた写真パネル──各園40枚ずつは作ってもらったので合計600枚以上──の貸出依頼なども、ときどき来ていたんですが、これも貸出依頼に必要な「写真一覧リスト」みたいなものがない。やはり作った方がいいだろうということで、サムネイル(*縮小した見本画像)付きのリストを作成しました。
──稲葉さんが学芸員として働き始めた当時、資料館には、どなたが詰めていたのでしょう。
当時の資料館は、大竹さん(*1)さん、山下さん(*2)もすでに辞められていましたし、平沢(保治)さんも、その頃は週に1回か2回来るか来ないかという感じでした。実際に毎日来ていたのは、佐川さん(*3)、あとは職員のOBで金銭の管理をしている方がいて、この2人だったと思います。
*1 大竹章(おおたけ・あきら)氏。全患協および全療協、多磨全生園の自治会活動、編集・出版活動などに長年関わったことで知られる。著書に『無菌地帯:らい予防法の真実とは』『らいからの解放:その受難と闘い』『ハンセン病資料館(佐川修氏との共編著)』などがある。現在94歳。
*2 山下道輔(やました・みちすけ)氏。全生園元自治会長、松本馨氏から依頼され、旧ハンセン病図書館で資料収集を40年にわたって続けた。資料へのこだわりぶりで各園からついた異名が『資料の山下』。2014年、86歳没。著書に『ハンセン病図書館──歴史遺産を後世に(柴田隆行氏との共著)』などがある。
*3 佐川修(さがわ・おさむ)氏。1928年韓国全羅南道生まれ(園の公式記録では1931年)。韓国名・金相権〈キム・サングォン〉。1964年に全患協の初代渉外部長に就任、全患協ニュースを担当する情報宣伝部長などを歴任。2006年より多磨全生園自治会長。『全患協運動史)』『倶会一処』の執筆(いずれも光岡良二、氷上恵介、盾木弘、大竹章、各氏との共著)も手がけた。2018年没。
山下さんは自治会図書室の方へ戻られていましたが、必要そうな資料があるとコピーを取って製本したものを持ってきてくださいました。そういう際にときどきお会いするという感じですね。一番身近にいた当事者というと、やはり佐川さんということになります。
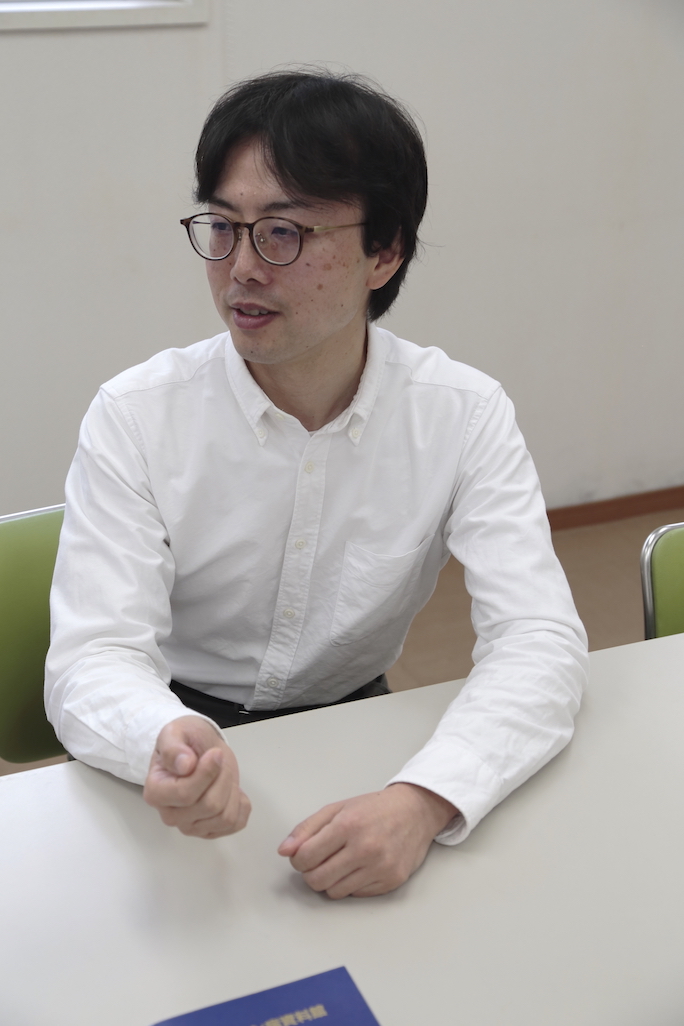
──佐川さんから「資料館の運営は、こうあるべきだ」みたいなレクチャーは、あったのでしょうか。
あらたまって(資料館運営について)どうしましょうか、と話した記憶は、あまりないです。佐川さんは午前中は自治会、午後になると資料館に来て、毎日同じ仕事を淡々と繰り返すという、そういうタイプの人でした。来館者の記録をつけたり、語り部の依頼が入っていれば語り部活動をする。それ以外の仕事に関しては、こっちも入ったばかりでしたし、あまり戦力になると思われていなかったんでしょう。佐川さんに「午前中、何をしていたらいいでしょう」と訊いたことがあるんですが、そのときの答えは「午前中仕事がないか。じゃあ(ハンセン病関連の)勉強でもしててよ(笑)」みたいな感じでした。
距離感を測りながら少しずつ
築いた、佐川さんとの関係
学芸員になってすぐ、佐川さんから高松宮ハンセン病資料館運営委員会発行の資料館パンフレット、北條民雄の『いのちの初夜』などを渡されました。今日は持ってきていませんが、『倶会一処(くえいっしょ。副題:患者が綴る全生園の七十年 多磨全生園患者自治会 1979年発行)』ももらったと思います。これを読んで勉強しなさい、ということだったんでしょう。『いのちの初夜』は、佐川さんが校正用に使っていたもののようで、あちこちにメモや書き込みがあるんです。もしかしたら間違えて手渡してしまったのかもしれません。

一緒に仕事をしているうちに、だんだんわかってきたんですが、佐川さんって、自分のまわりに壁を作ったり、ものごとを隠したりはしないんですが、こっちから聞かないと自分のことをなかなか話さない人なんですね。問わず語りに「おれ、こうなんだよ」みたいな話をするタイプではない。在日であることもまったく言わなかったので、もしかして隠しているのかなあと思ったんですが、じつはそうではなくて、聞かれれば言うけれども、聞かれなければ別段自分から言うようなことじゃない、そんな風に思っていたみたいです。
──新米学芸員である稲葉さんから見た、佐川さんの仕事ぶりは、どんなものでしたか。
佐川さんがしていた仕事というのは、僕が入る前も、入ってからもまったく変わらなかったと思っています。基本にずっとあるのは、「今ある資料館の姿勢をなにがあっても維持していくのだ」という考えかたなんですね。それを学芸員である僕らにも受け継いでほしいと思っていたのではないでしょうか。
1993年に資料館ができる前、佐川さんは大竹さんと一緒に全国の療養所をまわり、貴重な資料を集めてまわったわけですが、そのようなことがなぜできたかというと、全国の自治会、入所者の人たちとの信頼関係がまずあって、その上で任されたからだと思うんです。一方、佐川さんの側にも、託された信頼を裏切ってはいけないという思いがずっとあったのではないかと思います。
国が出してきた政策に従うだけ、あるいは国側の言い分をなぞるのではなくて、あくまでも自分たちが中心になって、当事者の歴史は当事者が残す。ハンセン病資料館の存在意義とは何かといえば、このポリシーを貫くことでしょう。
──常設展示の見せかたや企画展、あるいは書籍などを記念出版する際、佐川さんと意見がぶつかり合うようなことは、あったのでしょうか。
2003年に資料館十周年史を作ったときは、今まで資料館に展示図録というものがなかったので、「表向きは十周年史と銘打っているけれども、中身は展示図録というものを作ってはどうでしょう」と、こちらから提案しました。佐川さんはいいと思ったら「それいいね、そうしよう」と言う人なので、そのときは非常に反応がよかったです。逆にちょっとどうかな、気に入らないなと思っているときは、返事をしないで黙っているんですね(笑)。
あるとき、地方の療養所から借りてきた資料を一堂に展示するという企画展があったんですが、学芸員としては、あらかじめコーナー割などを決めておいて、テーマに沿って並べていこうと考えますよね。ところが佐川さんは、各園から借りてきたものを、一面にすき間なく並べて見せたい、と言うんです。
しかも絵を壁面に掛けて、そのすぐ下に壺とか置いちゃうんですね。もし絵が外れたら、壺も床に落ちて割れてしまう。これは危ないなあと思って、壺の乗ってるテーブルを手前にずらしてすき間を作っておいたんですが、佐川さんは、それがお気に召さなかったようで、次に見たときには元の位置に戻ってました。そういうところは、かなりはっきりしているんです。
──稲葉くん、あれじゃ駄目だよ、みたいな相談はなかったんですか。
そのときはお互い相談とかしませんでした。元に戻っていた壺を見て、こうじゃないと駄目なんだなと思いましたね(笑)。
佐川さんから面と向かってお前、なにやってんだと言われたことってほぼなかったですし、僕から佐川さんに「これは駄目ですよ」と言ったことも、一回しか記憶にありません。お互いになんとなく距離感を測っていて、こんな感じですよね、というところで意見の一致を見る。ずっと、そんな感じでやっていたんです。
国家公務員一般労働組合国立ハンセン病資料館分会 公式ホームページはこちらから
https://hansensdignity.com


